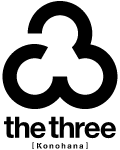REVIEW
岡本 啓 展を振り返って
開廊1年目のttk最後の展覧会となりました岡本啓展「Visible≡Invisible」、当展の枠組みであるGallerist’s Eyeシリーズは、作家の本来の表現とは別の切り口にて、作家の新たな展開や可能性を引き出すという趣旨を位置づけていました。岡本さんの主たる表現であるカラーのフォトグラムにも共通し、これまであまり表立って現れることの少なかった彼のバックグラウンドや細かなコンセプトを見せていくこと が、当展の主たる目的でした。
個々の作品の内容や配置、全体の流れはほぼ全て岡本さんによる提示ですが、先述の目的を実現するために、いくつかの条件を岡本さんに企画の段階で提案しました。彼のフォトグラム作品のハイライトでもある鮮やかな色彩を排除すること。彼の本来の作品の着想にある具体的なイメージを示唆させる内容とすること。(フォトグラム作品には比較的抽象的なフォルムが多いですが、彼の造形の原点には、感覚的なものよりも実体験を伴う具体的なイメージが中心であるためです。)そして、昨年のHANARARTの旧川本邸の展示でも実証された、彼の空間構成力を展示全体にて実現させること。これらを、当展のタイトルの通り「見えるもの(Visible)」と「見えないもの(Invisible)」の関係性を、全ての作品および展示に関連付けていく内容となりました。

当展をご覧になられた方はご存知だと思いますが、展示内で岡本さんが提示した内容は、容易にアクセスできない仕組みになっていました。作品群を前に、私や岡本さんの口頭による説明があって、全容が明らかになるものとなりました。 その状況については、一般的な展示であれば賛否両論があってしかるべきだと思います。しかし、本来の岡本さんのカラーフォトグラムの作品が、鮮やかな色彩によって鑑賞者の感性に強く働きかけるものであることに対して、当展の作品および展示は鑑賞者の思考や想像や理論的構築を積極的に喚起させていく対照的な構図になったことで、作家への新たなアプローチを提示するGallerist’s Eyeシリーズのコンセプトとも合致したものであったと認識しています。
本来提示する「見える」概念を提示する「写真」に対して、むしろ「写真のような写真」であるフォトグラムを扱う岡本さん自身は、当初から「見えない」概念に表現の重きを置いています。その意識を強調したため、当展の作品の多くは、表面上では制作過程や素材が非常に判別 しにくい作りになりました。それは自らの技術を誇張するためではなく、彼の表現の根底にある人間の視覚の曖昧さ・不確かさを訴えるものであり、その部分を鑑賞者により一層意識させるためには、種明かしとしての言葉・論理が必要であったと言えるでしょう。
岡本さんが当展で提示したコンセプトは、表面的・視覚的なものの背後・正反対の位置にある概念への意識、「二次創作」としての構築。そして、彼の具体的な着想イメージの代表的なものとして、「風景」という概念が提示されました。これらは個々の作品の中でただ別々に提示されたのではなく、複数の作品群によって連結され、かつ他の細かなコンセプトによるス トーリーの補完も加わって、一人の作家が作り出す一つの明確なストーリーとしての展示に仕上がりました。


個々の作品の細かな解説はここでは省略しますが、まず、2枚組の2種類で構成された《enlargement》は、過去に岡本さん自身が撮影した35ミリフィルムのごく小さな一部分を素材にした写真作品です。同一のフィルムから同じ範囲を取り込む際と最終的な印画紙への出力を、それぞれアナログとデジタルの互い違いで提示しました。岡本さんは、自らのフォトグラム作品について「写真の“ような”」という表現をよく使います。写真という技術が、一般的に私たちの視覚と記憶を補完する役割とするならば、彼が本来用いるフォトグラムという表現は、フィルムを介さない点で人間の視覚とは全く異なるものです。しかし、人間の視覚を切りとったものの象徴であるフィルムに、いわゆる人工的な現代の技術としてのデジタルとアナログの両義性を加えることによって、「見えない」という概念を私たちに提示するものでした。つまり、彼のフォトグラム作品は表層的であることを示しつつ、写真のフォーマットでありながら視覚の実態が伴わないという事実を表す、写真という技術に横たわる表裏一体性を浮かび上がらせることが、この《enlargement》の提示でした。

もう一つの当展での象徴的な作品群《彫刻》シリーズには、平面作品を中心に制作する岡本さんが、彫刻を制作するといういつもと違う制作行為を通じて、本来の表現の中にある一貫した思想を浮かび上がらせたものでした。一から彫り出したように見えるミニチュアの人物と動物の彫刻作品は、彼がフォトグラムでも使うような 「彫刻“的”」表現として、既製品のフィギュアの表面を薄く削り取っただけのものでした。中でも彼が強く主張したものは、「二次創作」の概念でした。彼の本来の表現であるフォトグラムの位置づけが、そもそも写真というすでに人間の手によって確立されたシステムかつフォーマットであり、そこからアレンジを加えたものがフォ トグラムであるという解釈において「二次創作」であるということです。真っ白なキャンバスに描いたり、自然の素材そのものからフォルムを彫り出したりするのではなく、すでに人間の手が一定のレベルで入っているものを加工することに、彼にとって思考や手作業としての造形をする上でのフィット感があるという主張です。

そして、今回の全ての作品群に、岡本さんの表現の着想となる具体的なイメージが共通して存在していました。岡本さんの幼少期からの日常にあった「風景」というものに、彼は常々自らの表現のルーツを直接的に重ね合わせていました。《enlargement》は使用された画像が地元の服部緑地で撮影されたものであり、《彫刻》シリーズの集合体としての《机上の空論》は、俯瞰視すると風景になりうるものであり、ホワイトキューブの窓際に設置したレンズとフィルムの作品と和室の一眼レフカメラのボディーと三脚による2つの《photographic memory》は、それぞれレンズ付近から向こう側に写る展示空間の「風景」を、鑑賞者が視認することができるものでした。
岡本さんが子供の頃に慣れ親しんだ大阪・吹田の千里地区は、ご存知の通り「千里ニュータウン」という人工的に作られた街です。建物はもちろんのこと、周辺にふんだんにある自然も街路樹や新たに造成された芝生など人の手があらゆるかたちで加わって形成された、いわば「二次創作」的な街です。あらゆるものに明確な意味や価値が存在して一見息苦しさを覚えることもあるかと思いますが、岡本さんにとってはそれこそが自らの心身共に馴染む感覚なのです。

私自身の「良い作家」の基準の一つに、「その作家がその作品を作ることに必然性があるか」という基準があります。その作家が幼少期から今に至るまでにどのようなものに触れ、どのような価値観を育んできたか。作家の常々の考え方の延長線上に、きちんと作品表現の軸が存在しているか。現代の美術では、マーケットや多様な立場でアートに関わる他者の思惑に引っ張られることにより、自分自身を偽るかのような虚飾ともいえる表現が生まれがちです。岡本さんの作家としての姿勢には、自らが美術の現場で活動することの理由を自己反省することが常に基本にあり、まさにこの「必然性」が彼の作家活動における最も中心の柱であることが当展でも証明されました。岡本さんの本来のフォトグラム作品は、特に表層的なイメージが強いだけに誤解を招くことも多かったですが、彼のフォトグラムでの造形の原点も身近な風景にあり、その首尾一貫性が作家としての信頼感にもつながっていると考えます。いわゆる時代性を隠喩として現すべきいまの現代美術の使命にも合致している表現を、岡本さんは以前から実践しており、当展は彼の自己反省の原点となって、ここで提示された表現のバリエーションは必ずや今後の彼の表現の新たな展開や深化へと向かっていくことでしょう。
Related Posts