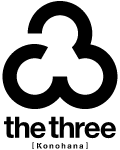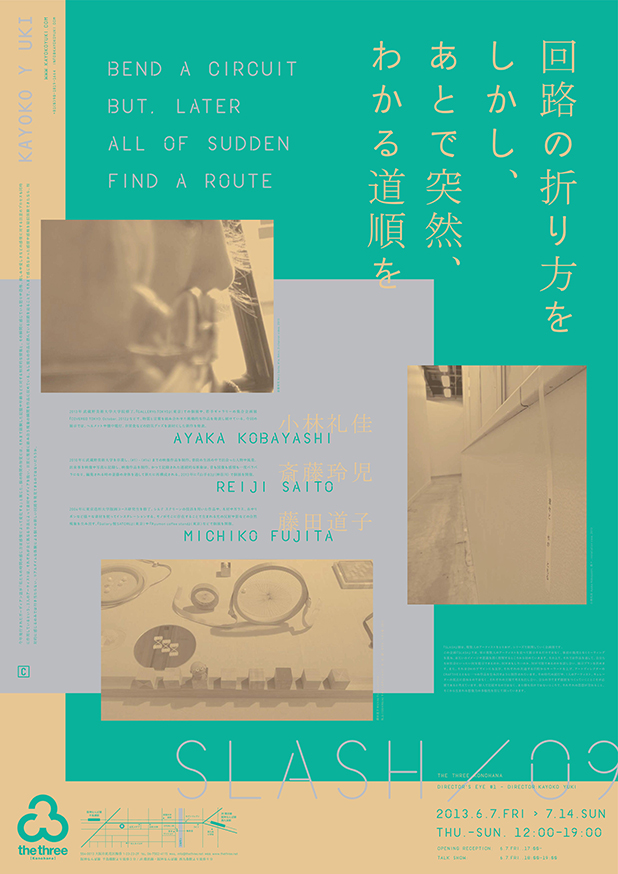EXHIBITIONS
2013-06-07Director’s Eye #1 結城 加代子 「SLASH / 09 −回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を−」
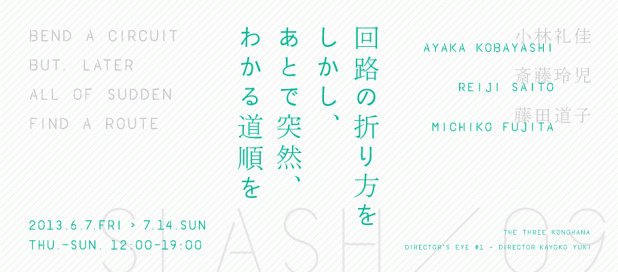
・「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」 展示風景
・「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」を振り返って
・SLASH/09展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介
Director’s Eye #1 結城 加代子
「SLASH / 09 −回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を−」
2013年6月7日(金)〜7月14日(日)
☆ 7月22日(月)まで会期延長いたします。
7月15日(月)~17日(水) 休廊
18日(木) 14:00~19:00
19日(金) 12:00~18:00
20日(土) 休廊
21日(日) 12:00~19:00
22日(月) 13:00~18:00 [再延長]
開廊時間:毎週木曜〜日曜 12:00〜19:00
休廊日:毎週月曜〜水曜
会場:the three konohana
展覧会ディレクター:結城 加代子(KAYOKOYUKI)
出品作家:小林 礼佳、斎藤 玲児、藤田 道子
デザインワーク:CRAFTIVE
オープニングパーティー:6月7日(金)17時〜
トークショー:6月7日(金)18時〜19時
* * *
Director’s eyeの第1弾は、結城 加代子(YUKI Kayoko, b.1980)の企画によるグループ展「SLASH / 09 -回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を-」を開催いたします。
結城は2011年に「KAYOKOYUKI」を立ち上げ、特定のスペースを設けず、独自の切り口による展覧会企画や、自らの取り扱い作家の企画やマネージメントなどを、東京を中心に精力的に展開しています。
彼女の仕事の中で特筆すべきものは、毎回異なる出品作家をセレクトしたグループ展シリーズ「SLASH」です。作家と共に幾度とミーティングを重ねながら、お互いの意識やイメージを共有させていくことから、企画作りは始まります。各作家およびディレクターの異なる個性を尊重しながらも自然と一つの磁場へと引き寄せるかのように、各人の思考やプロセスが丁寧かつ平等に積み重ねられて、一体感がみなぎる展示を毎回実現してきました。ディレクターの立場の人間が、作家と誠実なコミュニケーションをとって展覧会を作るということの、理想的なモデルケースの一つであるように思います。
彼女独特のバランス感覚に満ちたコミュニケーション力でもって、作家の新たな一面を引き出す手腕と、首尾一貫した思考と実行力による彼女の企画は、各所で高く評価されています。当展は、結城による展覧会企画を、関西で初めて開催するものです。この「Director’s Eye」シリーズは、展覧会を企画する専任ディレクターの育成とその役割の必要性を強調するための企画です。近年作家主導による展覧会企画が各所で目立つ中で、専任のディレクターによる企画から現れるべき思考やスタンスにおける客観性、そして作家とディレクターを分業することによって、展示および個々の作家のクオリティの向上をもたらすことの実効性を、彼女の企画を通じて強く実感していただける機会になればと思います。
the three konohana 山中 俊広
【当展趣旨】
このたびKAYOKOYUKIは、大阪市此花区にオープンしたばかりのギャラリースペース、the three konohana にて、連続シリーズ『SLASH』を開催致します。SLASH』展は、複数人のアーティストをとりあげ、シリーズで展開していく企画展です。
この企画『SLASH』では、単に複数人のアーティストを並べて展示するだけではなく、事前に幾度となくミーティングを重ね、お互いのイメージや意識を深く理解するところから始めていきます。その上で、それでは作品を通して、自分たちは社会にいったい何を提示できるのか、何がおもしろいのか、何が可能であるのかを話し合い、展示プランを決めます。また、それはDMのデザインにも及び、それぞれの共通する目的からキーワードを上げ、アートディレクターのCRAFTIVEとともに一つの作品を生み出すように制作されています。その時代の流行や、1人のアーティスト、キュレーターの視点に委ねるのではなく、それぞれの立場で考えを出し合い、自らの手でまず価値をつくっていくことこそが必要であると考えています。個人で完結するのではなく、また勝ち負けではないところで、それぞれの思想が交わること、そこから生まれる想像力の多様性を信じて探っていきます。
第9回目となる『SLASH / 09 -回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を-』では、小林 礼佳(KOBAYASHI Ayaka,b.1988)、斎藤 玲児(SAITO Reiji, b.1987)、藤田 道子(FUJITA Michiko, b.1980)の3人展を開催します。
小林 礼佳は、2013年に武蔵野美術大学大学院を修了し、GALLERY b.TOKYO(東京)での個展や、若手ギャラリーの集合企画展『COVERED TOKYO: October, 2012』などで、物質と言葉を組み合わせた挑戦的な作品を発表し続けています。今年行われた修了制作展においては、25平米ほどの白い空間に”く” の字型の壁を配置し、自身で紡ぎだした言葉を貼付けていきました。鑑賞者は、その始まりと終わりの不明瞭な途切れ途切れの文章を探しながらさまよい、一瞬ホワイトアウトしかける視点を、ふいに現れる言葉により現実につなぎ止められるような、複雑な感覚に陥ります。
斎藤 玲児は、2010年に武蔵野美術大学を卒業し、〈#1〉~〈#14〉までの映像作品を制作しました。最近では2013年に山手83(神奈川)で個展を開催し、最新作となる〈#13〉、〈#14〉を発表しました。日常的に撮影し続けている写真と映像を素材に、iMovieを使ったアナログに近い手法で切り貼りしていきます。かつて記録された連続的な事象は、音も図像も感情も一度バラバラになり、編集される時の斎藤の身体を通して新たに再構成されます。普段の生活の中で出会った人物、風景、出来事を扱いながらそこから一定の距離を保ち、あくまで絵の具やキャンバスなどの物質を扱うようにPCは操作され、決定されます。
藤田道子は、2004年に東京造形大学版画コース研究生を修了し、現在同大学にて非常勤講師として従事しています。シルクスクリーンの技法を使い、紙だけでなく布や鏡などの素材にもプリントする他、様々な物質を扱いインスタレーションします。薄い透明色のインクを使って、細い線の重なりによって描く幾何学模様や、木材やガラスに糸やリボンを組み合わせた作品など、モノがそこに存在することで生まれる光の反射や影などの自然現象を生み出します。Gallery惺SATORU(東京)やRyumon coffee stand(東京)などで個展を開催しています。
今年発行されたガーディアン誌が、「私たちの時間の感じ方は感情によって変化する」と報じました。脳の時間の知覚には、それまで経験した記憶や年齢などに対する相対的な情報と、その瞬間に感じている怒りや恐怖、親しみや愛しさなどの感情に対する注意のプロセスも同時に作用しているという研究結果でした。私たちには平等に一定の時間が与えられていながら、体験や経験によって、感じることのできる時間は伸び縮みしてしまうのです。 3人のアーティスト達は、それぞれが全く異なる手法によって素材やメディアを扱い、日常に複雑に絡み合う現象の瞬間を作品に収めています。もし彼らの作品に潜んでいる回路を辿ることで、それまで感じ得なかった感情や感触を疑似体験できたなら、相対的に感じるのみでは行き当たらない、リアルタイムな経験による個々の新しい回路を発見できるのではないでしょうか。
当展ディレクター 結城 加代子(KAYOKOYUKI)
※『SLASH』とは…ファンが作った2次創作作品(ファン・フィクション)の中で、キャラクター同士が結びつくようなカップリングを示す際に間にスラッシュ記号( / )を入れたことから、それらを総称して「スラッシュもの」と呼ばれています。
2013-03-15Konohana’s Eye #1 伊吹 拓 展「”ただなか” にいること」

・ttk開廊および伊吹拓展に関する、掲載プレビュー・レビューのご紹介
Konohana’s Eye #1
伊吹 拓 展「”ただなか” にいること」
2013年3月15日(金)~5月5日(日)
開廊時間:12:00~19:00 休廊日:毎週月曜~水曜、3月21日(木)
会場:the three konohana
the three konohana 開廊パーティー/伊吹拓展 オープニングパーティー:
3月15日(金)17時~22時
* * *
the three konohanaのオープニングは、関西を拠点に精力的に活動を続けている絵画作家、伊吹 拓(IBUKI Taku, b.1977)の個展を開催いたします。
近年の抽象絵画の動向には、従来の美術史の文脈の継承よりも、現代社会や日常の生活にある具体的な要素を取り入れて、再構成するものが目立っているように思えます。二次元上の造形という観点から、デジタルの概念が市民権を得たことによるレイヤー的な表現。個々人の精神の不安定さの蔓延が着想となっている超感覚的とされる表現。積極的な思考の放棄による単純な行為の反復・蓄積といったものが挙げられます。これらの背景には、従来まで絵画のアイデンティティであったはずの二次元としての画面や造形の概念が、副次的なものとして扱われるようになったことも要因としてあります。モダニズムが終焉して以降、あらためて絵画そのものの概念の行き詰まりを感じさせるとともに、それを再追究する余地はまだ残っていないだろうかという思いに駆られます。
伊吹は、自らの存在と内面の世界を深く洞察し、それらを発露させるための抽象絵画に、学生時代から一貫して取り組んでいます。なかでも、彼の特徴的な表現手法とされているものが、絵具による「積層」を通じて随所に発生する「垂れ」や「滲み」です。彼にとって筆や刷毛によるストロークと等価とするこれらの手法には、彼らしい感覚が横たわっています。それは「委ねる」ことです。
そこには、アメリカ抽象表現主義以来常に語られてきた、偶然性や自然的なものによる平面絵画内への関与を見ることができます。彼はこの他力としての要素を作品に積極的に取り入れ、更には自己にも接触させることによる流動的な変 化を強く意識しています。また、近年彼が取り組んでいる屋外での展示でも、日々の時間や天気における光の変化によって、常に同じ視覚認識で作品を鑑賞できない過酷な環境に作品を置きながら、伊吹は絵画そのものへ客観的なまなざしを投げ続けてきました。
当展は、これまでの伊吹の一貫した制作意 識から次の段階を強く示唆させる、新作のタブローのみで構成いたします。目に見えて力強さを帯びたストロークと色彩が画面上に刻み込まれ、これまでの調和感が強かった印象から、まるでその静寂を破るような画面が現れます。これまで「委ねる」という意識の下で自然に寄り添ってきた感覚から、積極的な行為とし ての「描く」ことへの渇望が強まったこと、それが彼の作品に変化をもたらしているように思います。画面上には主観対客観の単なる二項対立に留まらない、一 種の不均衡さが作品全体に漂っています。そんな複雑に入り組んだ両者の関係性が、画面上の情景に無数のバリエーションを生み出し、それらの中から彼は自らの手に委ねながら選び、掴み取っていく作業を積み重ねています。
感情という私的な概念はあくまでも画面の一部分に留まり、明確な行為としての筆致と色彩が、視覚的にも概念的にも画面上に明快なコントラストを生み出しています。それは絵画という概念の中に、客観性を備えた彼の主観の現れと考え ることができます。他力に依存する感情よりも自意識を強めた「描く」行為を通じて、絵画への客観的なまなざしを向けること。当展において伊吹は、これまでの作家活動の中で見い出したあらゆる要素を全て画面上に撒き散らし、自らの絵画を構成する物事や概念、価値観、それらの境界線などの、まさに「ただなか」 に我が身を置くことになるでしょう。
弊廊のオープニング展は、あえて絵画そのものの概念や本質についてじっくりと考える機会になればと思います。ぜひご高覧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

《midst》油彩、綿布 162 x 162 cm 2013 【当展出品作品】