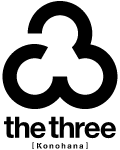REVIEW
『続・まよわないために -continuation of ”not to stray”- 』 text: 野口 卓海
いまさら「世代感覚」について語るという徒労さや気恥ずかしさを充分に理解したうえで、それでもなお私は自分の同世代(*1)について一度考える必要を感じていた。それは作品の表面的な部分に散見される具体的な傾向や、コンセプト及びステイトメントで頻繁に用いられるキーワードの検索結果ではなく、むしろそういった安直なる捉え方をしばしばされてきた同世代への、皮膚感覚を伴った(自己)言及のような接近を試みたかったのだ。
この世代の大きな特徴としてやはりまず触れなければならないのは、情報を司る媒体の非常に大きな変遷をおよそ思春期に経験しているという点である。情報技術の革新にまつわる様々な変化を、私たちはその身をもって目撃・経験したという事だ。勿論、その変化は上の世代にも大きく関係していたが、それは仕事や社会生活への影響が割合として色濃く、1995年前後に小学生~高校生であった私たちが体感していた「まさに(身体的にさえ)浸透していくような」、無意識的で受動的な移り変わりではなかっただろう。気がつけば、あたり前のように受け入れていた、世界の様相の変化。新聞やテレビだけが担っていた報道が最早一方向ではなくなり、通信技術の発達は距離や時間の感じ方・意味合いを極端に変えた。また、未だに増え続ける巨大なデータベースの出現は、本来不可視でありながら自明の権威を持っていると思われていた様々な価値基準を並列化し、そしてそれらへのアクセスを瞬時に行えるようになった。崇高な絵画と下世話なポルノが、なんら価値の差異なく.jpgという同一の拡張子をまとってディスプレイに浮かび上がり、センセーショナルな報道写真の後に見知らぬ誰かのプライベートなスナップを覗き見るという経験さえ、私たちにはごく日常的な行為となってしまった(*2)。これまでは誰かが編集を加え、一定の視座に則って整理していた情報を、自らが思うまま整列(ソート)する事が私たちにとって当然の習慣となった(*3)。影響の深度は違えど私たちが凡そ同じ時期に通過してきた、情報や価値に巻き起こった地殻変動は、例えば「パラダイムシフト」や「物語の終焉」と名づけられてきただろう。しかし、その”名づける”という行為自体は、常に外部からしか行われえない(*4)。上記のような状況を身をもって体感し、その上であたかも呼吸するかのように適応していった(適応せざるを得なかった)のは、他ならない私たちの世代なのだ。そして、身の回りを擦過した加速度的な変化は、この世代だけが経験した特有の通過儀礼であったと言えるだろう(*5)。
では、その共通して経験した通過儀礼は、どのような形で現在に影響しているのだろうか。同世代の大きな特徴としてまず私が指摘したいのは、現代美術が抱えていた「新しさ」という病からの開放である。上述の通り、情報がことごとく並列化していく状況に慣らされた私たちは、最早「新しさ」に対して不感症になっていると言えるだろう。情報をソートする基準のひとつとして未だに機能しているが、それは絶対的で権威を持った指標ではなくなった(*6)。また、「メインストリーム」や「サブカルチャー」といった住み分けも、この世代にはほとんど意識されなくなっている。上述した大きな変化の只中に身を浸すようにして中高生を過ごした私たちは、趣味や感性に影響を及ぼした媒体が単一ではなかった為、それまでに比べ画一的な流行も起こらなかったからだろう。音楽を例に挙げると、J-POP・アイドル・ヴィジュアル系・メロコア・HIP HOP・テクノ・ロック・クラシック・フォーク・・・と、時代・ジャンル問わず何を聴いていてもおかしくはなかった。そういった「メイン」や「サブ」という安易な境界も、私たちの世代ではほとんど意識される類のものではなくなっているのだ。そして、それは「カウンター」すべき共通の敵すら存在しなくなった事を意味する。
そういった幾つかの特徴からは、あたかも各個人の価値基準や趣味判断を確固と自立している世代のように読み取れるかもしれないが、残念ながら実態は全くそんなことはない。今回の企図でも触れたとおり、むしろ表現という地平では、大いなる目的地が失われてしまっているため、常に各々が戸惑い不安に満たされている。今回の「まよわないために -not to stray-」で取り上げた四組五名の作家が、染織・絵画・彫刻・音楽と全く違う分野でありながら、それぞれの技法と素材に対して着実な積み重ねとまなざしを共通して持っていたのは、そういった出自への意識自体が戸惑いや不安に対抗する有効な手段であるからだ(*7)。先ほど触れた「新しさ」だけを追い求めない世代感覚も、恐らくこの態度への理由のひとつであるだろう。また、そのような着実な表出を「モダニズムへの回帰」という言葉で指摘しうるかもしれないが、しかし上述の「並列化された情報へ瞬時にアクセスし、それらを自らがソートする」という我々に最も馴染んだ物事との距離感から鑑みると、これは「回帰」と呼べる姿勢ではないだろう。偶然目にした古い映画がちょっと面白くて見ている、ぐらいの感覚かもしれない。むしろ重要なのは、技術(テクネー)の集積に対し彼らは素直に肯定的で、技術を心強いパートナーと認識している所だ。それは美術史の中で激しくゆれ動いていた、「技術への敬虔な信仰・信奉」と「技術への極端な嫌悪・排除」という双方から距離をとった場所で、対等に技術と戯れているということだ。表現の地平から全員が目指すべき大いなる目的地が失われ、ほとんど荒野のようになっているからこそ、無邪気に技術と遊ぶことが許されているのかもしれない(*8)。この共通した態度も、今回発見した同世代の特徴として付け加えるべきだろう。
それぞれの命綱を握り締めながら、単一の目的地もなく歩きまわる同世代が生み出しているシーンを、最早文脈化することは不可能なのだろうか?私はむしろ、そういった状況でこそ起こりうる思いがけないリンクや飛躍、つまり作家同士の足跡がふっと重なったり方向性が近寄ったりする瞬間にこそ、俯瞰的な立場からの言葉や企画による介入が必要だと感じている。会期半ばに開催したトークの終盤でも少し触れたが、私たちの世代がさらされ続けている現状と、その只中で絶えず流動している作家達のネットワーク自体の保存を目的とし、相関図ほどドライでもなく図鑑ほどマクロでもない、ある種蠢動する地図のような代物を私は作りたいと思っている。個人・シーン問わず私達の世代と地域が抱えている熱量や生々しさを、そのまま採集しておきしたいという私の欲求は、一方向かつ画一的な文脈化への抵抗でもある。本来は、烙印にも似た他者による”命名”へ対抗するような、一人称複数形の自己紹介が必要かもしれないが、恐らくその話法を私たちはまだ知らない。表現の荒野あるいは迷宮でまよわないためには、時折後ろを振り返り自らの足跡を確認するような態度が必要だったが、この次は恐らく前方へ発声するような振る舞いが求められるのではないか。もしかすると、私たちはまだ本当の意味でお互いが出会っていない可能性さえあるのだから。
2014年3月8日 野口 卓海
———-
*1:本テキスト中で私が”同世代”と認識しているのは、年代による区別ではなく1978~1988(1983±5)年生まれである。
*2:そういったテクノロジーの進化による従来の価値基準の瓦解は、リキテンスタインの”積みわら”等に代表されるように、20世紀半ばのポップアーティスト達が盛んに作品の主題としたものだ。しかし、印刷技術の発展に伴った当時の変化よりも、情報技術による世界の並列化は、物理的な質量を一切伴わない点において、より広範かつ強烈だ。
*3:その習慣の発展は、自己の住み心地だけを重視した属性で充満するタイムライン(TL)の生成を促している。タイムラインという構造・インターフェイスは、あたかも共通の現在形を過ごしているかのような幻想を私たちに抱かせるが、同一のタイムラインなどはほとんど存在せずに、膨大なTLが少しずつズレて積層しているだけに過ぎない。それは、内外や受動・公私といった本来社会的には二分されていた事柄を、非常にあいまいにし見えづらくする性質も持っている。
*4:俯瞰の立場にいる他者(しばしばそれは年長者であり、部外者である)により私たちに与えられた”名”の例として、「酒鬼薔薇世代」「キレる17歳」「ゆとり世代」「プレッシャー世代」などが挙げられる。
*5:そういった情報技術が、「まだなかった」でも「すでにあった」でもなく、グラデーション的に変化していったという点において、もう二度とない特有の共通した経験を私たちは通過している。
*6:私たちが情報や事柄をソートする基準は、常に複数存在する。表現の主題やコンセプトの焦点を、作品ごと・シリーズごとのみなら、同一作品の内部でさえ目まぐるしく変化させる作家が増えていることも、その影響かもしれない。
*7:このような落ち着いた態度は、私たちの世代がバブルだけでなく所謂アートバブルもそれ程経験していないことも理由のひとつかもしれない。
*8:こういった技術との関係性は、RPGのレベル上げに近いのかもしれない。それも、共通のラスボスや確かなシナリオを持っているタイプのゲームではなく、多人数参加のオンラインゲームのようなイメージだ。翻って、村上隆の個展タイトル「召喚するかドアを開けるか回復するか全滅するか」(2001年 / 東京都現代美術館)からは、シナリオが明確なRPGへの暗喩が強く感じられる。村上の世代にとっては、大いなる目的地も、そこへたどり着く攻略法も、非常に困難であったとしても確かに存在していたのかもしれない。
Related Posts