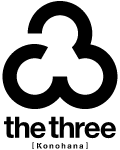REVIEW
「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」を振り返って
ttk開廊2つ目の展覧会となりました「SLASH/09 回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」。
ttkの企画の3本柱のうち、作家ではなく専門ディレクターを招致しての企画「Director’s Eye」シリーズのこけら落としとして開催したものですが、ここにはディレクターの結城加代子さんの企画の意図が、ttkの現代美術に対する向き合い方と自然と合致した様を提示した内容となりました。
当展のタイトル「回路の折り方を しかし、あとで突然、わかる道順を」の通り、この展覧会の最大の目的は、鑑賞者に対する展覧会における鑑賞態度への提言だったように思います。まず展示スペースに入ったときのここの作品の印象が強くないこと、どこからどこまで(何から何まで)が「作品」なのかどうか、一見意味深には感じられるがこの作品配置に何の意図があるのか。この展覧会で4人が作った世界観は、いかに直接的なアプローチを避けるかという点にあったと思います。空間全体を概観しただけでは、何かここにあるのかはさっぱり分からない。そのためには個々の作品へと視界を絞っていく。その中で3人の作家の個性やテーマを読み取り、この3人の表現をどのようにカテゴリー分けしていくか。そこにはもちろん唯一の答えがあるわけではありません。その答えのごとに空間内の地図は複数発生していきます。この展覧会は鑑賞者の数だけその答えがあるというアプローチの元に、計算されて作られたものでした。これから述べる内容は、あくまでも私個人が見て自分の頭の中で作った地図です。

まず、ホワイトキューブの展示から。この空間の展示が、まさにこれぞSLASHと言える作り方で出来上がったものです。作家3人の領域分けは明確だったものの、4人の意思疎通の中で明確に一つのコンセプトによる展示を作ろうと現場で苦心したものでした。この空間においては、作品に直接ベクトルが向く「かたちを認識する視覚」という、一般的な鑑賞で用いられる感覚に頼れない空間だったように思います。
藤田さんは、今回糸の作品を多用し、特に壁面2面を使った大規模なインスタレーションが印象に残っていると思いますが、実は糸の存在にその実態があるのではなく、糸が空間に差し込む太陽光に作用する、そのわずかな変化にその実態がありました。つまり、複数の糸の色が光や白い壁面、または糸同士が交わることで生じる色彩の変化は、糸そのものよりも、それに隣接する空気や空間に視点が向けられていきました。
小林さんは、素材に使った防災グッズよりも、そこに付与される彼女の詩の存在。作家の主観性が入るような手書きの文字ではなく、全て活字によってシートや切り文字として起こされた文字の集合体には、かたちについての意味性はなく、あくまでも文字による情報として、鑑賞者へ提示されていきました。各々の詩によって、防災グッズの意味性を解体するのは本来の小林さんの表現のコンセプトでもありました。
斎藤さんの2種類の映像は、彼自身の日常的な視点を断片的に切り刻み脈略を失くすかのようにつなげていくものですが、彼の映像で強調されるべきは「リズム」です。動画と静止画が切り替わるタイミングと個々の投影時間、そして映像にリンクされる時とされない時がある音声。視覚で受ける「像」はあくまでも「イメージ」に過ぎず、ここに彼の身体性を求めるならば、実体あるものは彼が編集という行為の中で恣意的に作り出した「リズム」に注目すべきなのです。
以上の各作家のアプローチから、当初の想定どおり多くの鑑賞者の方々がこの展示に戸惑ったわけです。視覚に頼らないこととしながらも、個々の作品は物質性を強調しており、視覚での認識へと誘導されざるを得ないものでもありました。しかし、視覚だけでは解答の導きには限界があり、まずは視覚以外の感覚からこのホワイトキューブの展示は読み取るべきであろうと思いました。

そして、奥の和室からベランダへと流れるもう一つの空間。個々の作品作りはホワイトキューブと同じでしたが、どちらかというと個人担当制で作られた展示でした。しかし、この空間に対する取り組みは、ホワイトキューブとは対極の有機的な「サイトスペシフィック」であったと思います。
前回の伊吹展での使い方から一変して、非常にシンプルな展示になりました。このシンプルさは、もちろんホワイトキューブの展示と共通するものですが、そもそも空間自体の意味やシステムが対照的なので、近い手法を取ってもその表現は大きく変化します。そんな展示手法を取って提示したものは、このttkの和室展示室の細部への誘導でした。和室内は、藤田さんと小林さんが照明に施したコラボレーション作品のみ。それによって、室内の畳や窓やふすまや天井に至るまで、鑑賞者の方の視線は和室空間全体へと大きく動くことになりました。前回の伊吹展よりも、お客さんの和室に対する反応が特に多かったことがその現われだと思います。
ベランダ手前の土間付近に藤田さんの小品が複数並んで強弱をつけた後には、最後のベランダでは、1階へ降りる階段に斎藤さんのミニシアターが登場しました。特に最後の斎藤さんのベランダの作品は、ホワイトキューブで流された映像とは異なり、比較的長回しの映像素材が中心で、音声も映像とリンクしているものが多い作品でした。つまり、このttkの和室空間は、かつての生活環境を想像させる実体感のある空間として、その実体あるものとは何かを確認するために、もう一度視覚に戻るというアプローチだったのではないでしょうか。

そもそも、この展示のコンセプトは「美術の展覧会を鑑賞することにおける、鑑賞者への態度の問いかけ」でしたが、その「視覚/見る」行為というものに焦点を当てるために、その周辺へと関心を誘導するものだったのではと思いました。もちろん「見る」ことが、ただ色やかたちを把握するだけではありません。しかし、どうしても答えを拙速に求めるあまりに、視覚以外の感覚をなおざりにしがちです。けれども、最終的には「視覚」は美術表現を読み取るためには必須の感覚です。そうした「道順」を鑑賞者が各自で見つけ出していく。その大切さを伝えようとした企画が、このttkで繰り広げられたSLASHだったのだと思います。
ttkの今後の企画でも、この結城さんたちが実践してくれたアプローチを意識して、鑑賞者の自発性をさらに喚起させる企画を作っていきたいと思います。
Related Posts